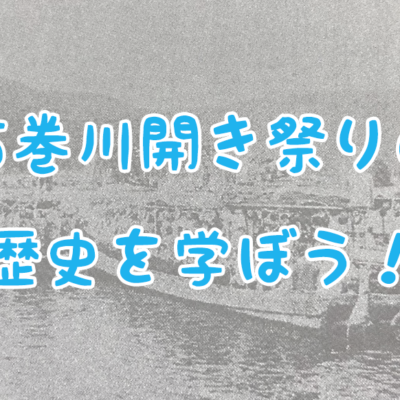2020
06.25
06.25

七夕飾りのはじまり
①日本の伝説

夏場の冷害から守り、食べ物がたくさんとれるようにと、田んぼの神様に願ったことから七夕という習慣が生まれました。そのとき、竹や笹を飾って田んぼの神様をよびこむという行事が習慣になっていったのです。
②中国の伝説

おりひめ、ひこぼしという2つの星は次の意味があると考えられていました。
・おりひめ(琴座のベガと呼ばれる「織女星」→縫製の仕事
・ひこぼし(鷲座のアルタイルと呼ばれる「牽牛星」→の農業の仕事を司る星
この2つの星は1年の中で7月7日に天の川を挟んで最も光り輝くことから、この日を巡り合いの日と考えられていました。
■仙台の地での広がり

田んぼの神様、おりひめとひこぼしの伝説などの要素が絡み合って日本の七夕祭が生まれて、継承されてきました。
江戸時代初期、仙台藩祖の伊達政宗には婦女の文化・知識を高めたいという思いがありました。
その想いから、七夕を開催することを進め、当時は江戸で年中行事たったものを真似して開催し始めたそうです。
その後だんだんに盛んになり年中行事の1つになったとつたえられています。
石巻には、大正時代からまちの商店街のおみせの人が中心に、吹き流しの七夕飾りを飾り始め、いまでもその文化はつづいています。
■七つ飾りの意味

・短冊-学問や書の上達の願い。
・紙衣-病や災いの身代わり、または、裁縫の上達の願い。
・折鶴-長寿の願い。
・巾着-富貴と貯蓄、商売繁盛の願い。
・投網-豊漁を願い。
・くずかご-飾り付けを作るとき出た裁ち屑・紙屑を入れる。清潔と倹約の願い。
・吹き流し-織姫の織り糸を象徴。